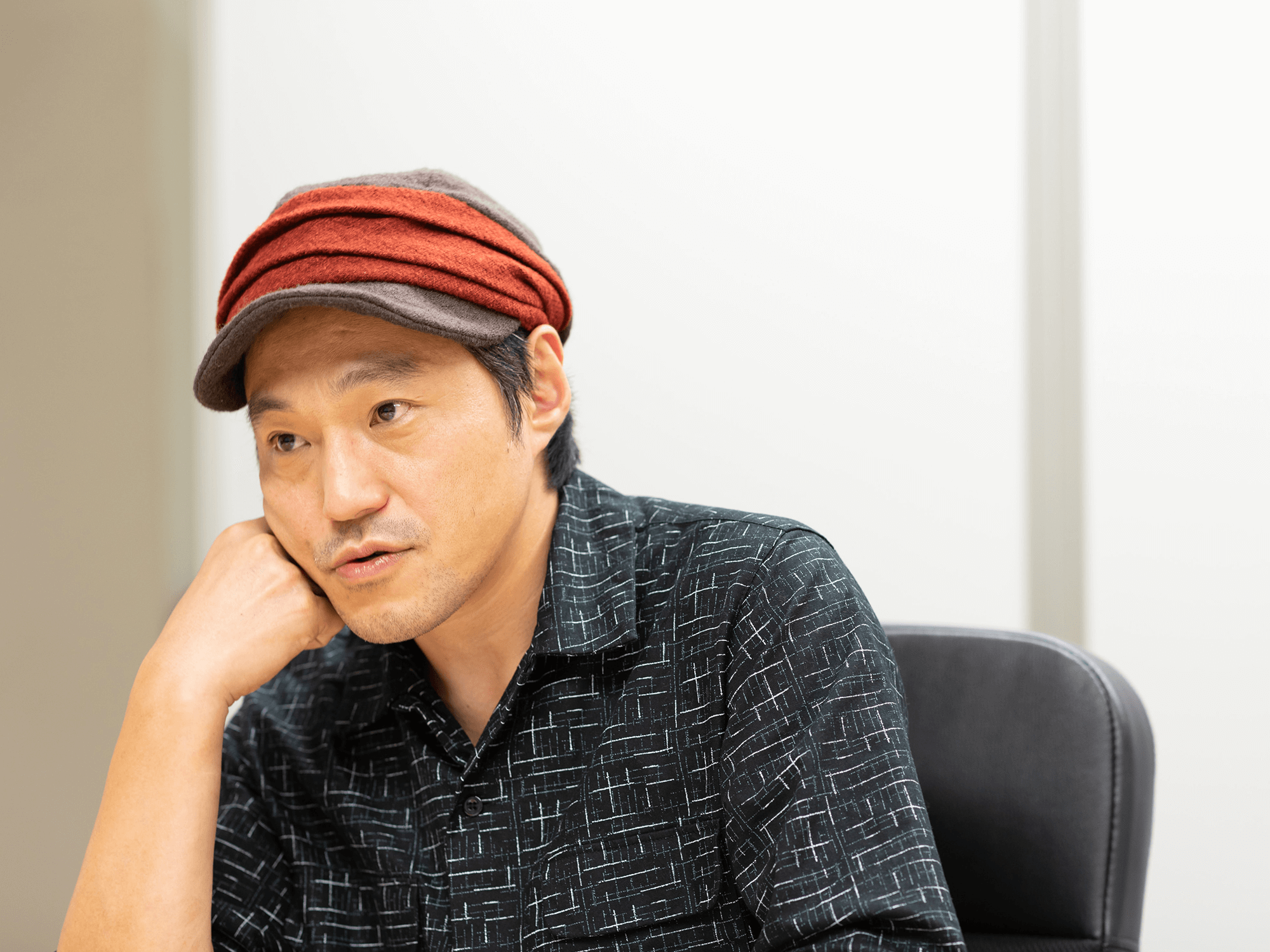役者の実在感にもディテールを効かせる
Q:役者さんも時代ごとの雰囲気を身にまとっていて素晴らしかったです。
冨永:僕は世代的に(1975年生まれ)映画で描かれる時代をリアルな実感を持って生きてきたわけではないので、人物的な佇まいというのも想像でしかないんですが。
ただ役者さんの側……特に笛子(主人公・末井昭の愛人)役の三浦透子さんは、もしかしたら年代記の中の一ページに登場する人物の実在にアクセスすることを必死で考えてくれたかもしれないです。というのは、笛子のモデルになった女性が『ウイークエンド・スーパー』(1977年~に末井昭が編集していた伝説の雑誌)の編集後記に毎月文章を書いていたんです。一年間か一年半くらい。そのコメント程度の短いテキストの連なりの中に、彼女の人間性が生々しく垣間見えるんですね。
それを自分が見つけた時はドキドキしました(笑)。で、この編集後記を三浦さんに見せたんです。これは演じるうえで相当影響あったと思いますね。三浦さんは時折、この登場人物を「笛子」という役名じゃなく本名で呼んじゃったりしていたくらいなので。

Q:いい話ですねえ。
冨永:この彼女は、きっと当時かっこいい女の子だったと思うんですね。文章の書き方も結構とんがった感じで。末井さんもこの方のことは特別に好きだったと思うんですよ。『自殺』(2013年/朝日出版社)という著作でも、「Fさん」という呼び名で彼女のことに触れている箇所は文章のタッチがまるで違いますからね。
だから僕は笛子のモデルになった当事者の女性が、この映画をどこかで観てくれることを期待しながら作ったところがあるんです。ご本人に観られても恥ずかしくないように……そこはものすごく緊張感を持っていました。
Q:なるほど。あと登場人物たちのメガネがやたら曇っている、という指摘は多かったですよね。
冨永:僕の仮説としては日本が猛烈な経済成長期で、男たちがみんな死にもの狂いで働いていたという時代背景がある。だから服が汚れていても、メガネが汚れていても一向に平気で、キャバレーの店長(政岡泰志)に至っては病院で手当てしてもらった大怪我すら気にしていない(笑)。
この点はもうちょっと象徴的な意味を持たせていて、主人公の末井青年(柄本佑)にとって、自分のことを理解してくれない人物……つまり労働することに疑問を持っていない人たちほど、メガネが汚れていて、横暴な口をきいて、怪我をしているんです。キャバレーでも工場でもデザイン会社でも、その他大勢って感じですね。主人公の妻・牧子(前田敦子)さんはメガネをかけても汚れていないんです。父・重吉(村上淳)は工場にいる場面だけメガネが汚れている。
全体的には、みんなが思考停止になるほど労働に従事していた時代の中で、主人公だけが屈託を抱えていたっていう風に、さりげなく見えたらいいなと思っていたんですけど、ちょっとやり過ぎたかな(笑)。

Q:いや、すごく効果的だったと思います。狂騒的な時代の中で、末井青年だけが飄々と浮遊しているようにも見える。神は細部に宿る、というように、ディテールを詰めているからこそ我々も映画の世界にすっと入っていける。
冨永:だと嬉しいですね。これまで、ディテールは現場で思いつくことが多かったんですけど、今回のメガネに関しては衣装合わせの時に、ふと「こんな綺麗なメガネじゃないな」と思って。最初の発想はまったく感覚的なもので、あとから具体的な理由がついていった感じです。