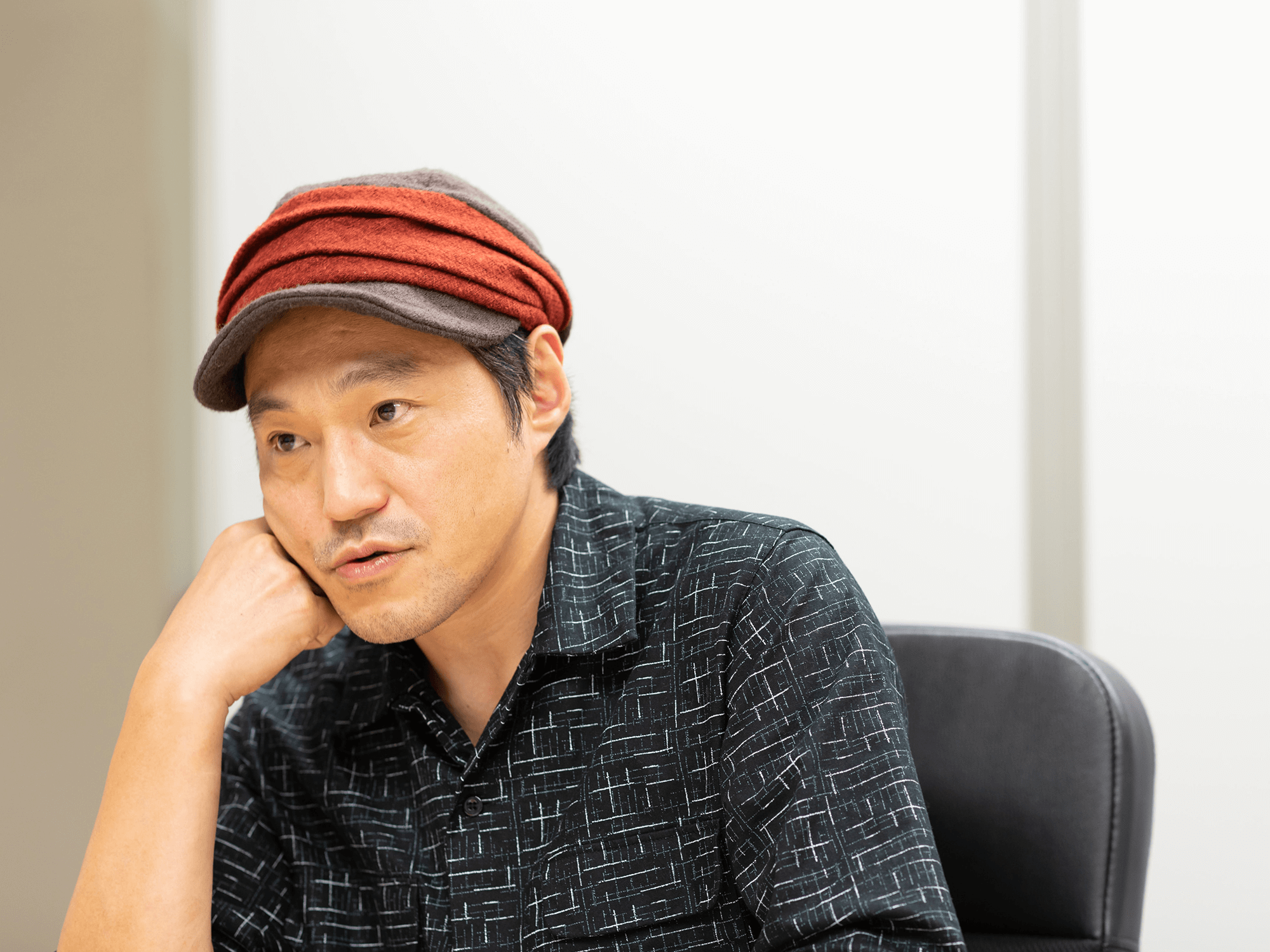マーティン・スコセッシ映画と、諸行無常
Q:クロニクル映画特有の「諸行無常」感も『素敵なダイナマイトスキャンダル』はものすごく良く出ていたと思います。猥雑でアナーキーな70年代、小綺麗な80年代という風に、時代のカラーが容赦なく変わるようなところがありますね。
冨永:確かにそうですね。70年代にメガネを曇らせていた人たちが、80年代にはどんどんフレームの外に消えていっちゃう。ある程度、時代を跨いで登場する人物っていうのは末井青年と、奥さんの牧子さんと、キャバレー時代の同僚からエロ雑誌の世界に主人公を橋渡しする中崎(中島歩)って男くらい。「その他大勢」の人たちは、その時代の一期一会の風景として通り過ぎていく。
牧子役の前田敦子さんに関しては、僕の大好きな『グッドフェローズ』(1990年/監督:マーティン・スコセッシ)のロレイン・ブラッコをイメージしていました。カレン・ヒルというマフィアの妻役なんですけど、最初は可憐な乙女だったのが、だんだんガサガサのおばさんになっていく(笑)。アウトローの世界に日常的に染まって、完全に仕上がっていく感じになればいいなあって。

Q:よくわかるなあ(笑)。スコセッシはクロニクル映画の黄金形を諸作で提示していますよね。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2013年)のバカ騒ぎ感、ヤバいことで儲けまくってる会社にFBIが乗り込んでくるところとか、『素敵なダイナマイトスキャンダル』に近いノリがある。
冨永:はい、やっぱり意識しましたね。スコセッシが凄いなと思うのは、年を取ってからの方がバカになってるという(笑)。初期はやっぱりイタリア・シチリア系移民としての自意識の周りをぐるぐる回っていたけど、だんだんパカーンと解放されちゃって。
自分の映画もあれくらいバカ全開でずっと押したかったんですけど、必然的にそうはなりませんでしたね。主人公がダウナーに傾いていくので。
Q:祭りの終わりと共に後半は黄昏ていく。時間の流れ方や体感の密度も変わりますよね。その意味でも1970年代末から80年代にかけての米ポルノ業界の光と影を描いた青春映画『ブギーナイツ』(1997年/監督:ポール・トーマス・アンダーソン)と比較する声は多かった。
冨永:そうですね。もちろん題材的にも時代的にも『ブギーナイツ』や、あとポルノ雑誌『ハスラー』の創刊者を描いた『ラリー・フリント』(1996年/監督:ミロス・フォアマン)なんかは早い段階から頭をよぎってはいたんですよ。ただ考えれば考えるほど、末井さんとの違いしか思い浮かばなくて(笑)。
特にラリー・フリントというのは、真正面から権力と闘っちゃった人じゃないですか。末井さんの場合は「闘わずにして、どうすり抜けるか」っていう。ポルノグラフィーを通して国家権力と対峙した点は共通しているんですけどね。ただ末井さんを通すと、権力の方が矮小化される可笑しさがある。

前半と後半のタッチの違いってことで言うと、厳密には『素敵なダイナマイトスキャンダル』の原作って二つあるんですね。ひとつは末井さんが若い頃に書いた同名のエッセイで、もうひとつは近著の『自殺』。この「文体」の違いに強く影響されて映画を作ったわけです。祭りの真っ最中にいる末井さんが現在進行形のことを書いた本と、年を重ねた末井さんが昔を振り返りながら書いた本では、当然「文体」から伝わる時間の体感や流れ方も変わってくる。それをなるだけ忠実にというか、自分なりの変換作業で映画に刻みたかったんです。