映画『エゴイスト』が纏う独特の空気感。観始めるとすぐそれに気付かされる。張り詰めているようで柔らかい、冒頭から続くその空気感は、まるでこの映画の決意表明のようだ。漂い絡み合う視線と肉体、それに肉薄するカメラ。この映画の“本気”が観る者に迫ってくる。
主演の鈴木亮平と宮沢氷魚、そして監督の松永大司は、いかにしてその空気を作り映画に焼き付けたのか。3人に話を伺った。
『エゴイスト』あらすじ
14歳で⺟を失い、⽥舎町でゲイである⾃分を隠して鬱屈とした思春期を過ごした浩輔(鈴木亮平)。今は東京の出版社でファッション誌の編集者として働き、仕事が終われば気の置けない友人たちと気ままな時間を過ごしている。そんな彼が出会ったのは、シングルマザーである⺟(阿川佐和子)を⽀えながら暮らす、パーソナルトレーナーの龍太(宮沢氷魚)。自分を守る鎧のようにハイブランドの服に身を包み、気ままながらもどこか虚勢を張って生きている浩輔と、最初は戸惑いながらも浩輔から差し伸べられた救いの手をとった、自分の美しさに無頓着で健気な龍太。惹かれ合った2人は、時に龍太の⺟も交えながら満ち⾜りた時間を重ねていく。亡き⺟への想いを抱えた浩輔にとって、⺟に寄り添う龍太をサポートし、愛し合う時間は幸せなものだった。しかし彼らの前に突然、思いもよらない運命が押し寄せる――。
Index
本編に採用された即興劇
Q:劇中の二人の佇まいがとても自然でドキュメンタリーのような空気も感じます。監督からお二人へはどのようなことを話されたのでしょうか。
松永:基本的な役作りは衣装合わせのときから始めましたが、クランクイン前に1週間ほどリハーサルの時間をもらい、そこで一緒に作っていきました。ただし二人には、「こうしてほしい」みたいなことは言っていないと思います。
鈴木:監督のこれまでの作品を観ていたので、いわゆる“お芝居”は嫌うだろうなと。なるべく自分の中で嘘がないように役を生きたいと思っていました。そうしたら、リハーサルの最初からエチュード(即興劇)が始まった。「ああ、そうか。やはり本当にその人物になりきることを求められている作品だ」と。
松永:リハーサルには撮影監督にも来てもらい実際にカメラで撮ってもらいました。最初は、龍太が母親の妙子を浩輔に紹介するシーン。龍太が買い物に行き浩輔と妙子が二人きりになるところから始めて、「さぁ、二人きりになったらどうする?」と。そこは台本に無いシーンなので、こちらから動きやセリフを伝えることも特にしなかったです。
鈴木:よくワークショップなどであるのは、撮影するシーンの直前に起こったことを即興でやり、そこから実際のシーンにつなげるもの。でも今回は、その即興部分も本編に採用されたんです。「自分たちがその場の気持ちで言ったことも、どうやら映画にしてくれるらしいぞ」と(笑)、そんな空気になっていました。
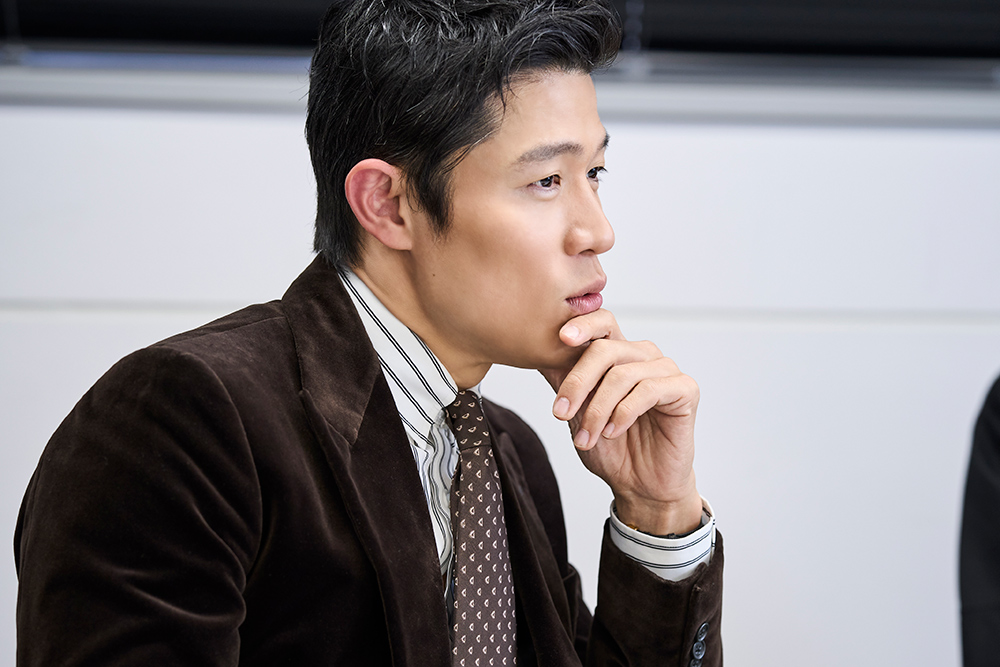
『エゴイスト』鈴木亮平(斉藤浩輔役)
松永:僕も氷魚も別室のモニターから浩輔と妙子のやりとりを見ていたのですが、氷魚が楽しそうに言うんです「なんかすごく良いっすね」って(笑)。もちろん僕も良いと思って、それでそのまま本編に採用しました。
宮沢:こんな演出は初めてでしたね。他の現場では、台本に書かれていることを忠実に芝居で表現していくのが基本。でもこの現場では、物語の流れはありつつも、シーンの目的に辿り着くまでのルートは僕たちに任せてくれた。ルートを強制されることはなく、その瞬間に出て来た言葉や表情、感情を全部汲み取ってくれたので、こういう映画になったんだと思います。
やってる僕たちもどうなるか分からない瞬間があったし「次はどういうリアクションをするんだろう」「どういう言葉が出てくるんだろう」と、全てが生っぽくてリアルでした。どの現場もこういう贅沢な環境だったら良いんですけどね。
松永:僕もここまでのことは初めてなんです。これまでもやってみたかったけど、全てのピースが揃わないと無理でした。また、映画によってはこの方法で撮らない方が良いものもある。例えばアクション映画では絶対出来ないこと。亮平と氷魚、阿川さん、撮影監督の池田(直矢)、スタッフ、そしてこのテーマだからこそ出来たもの。皆で何が出来るかを確認しながら前に進んでいきました。


