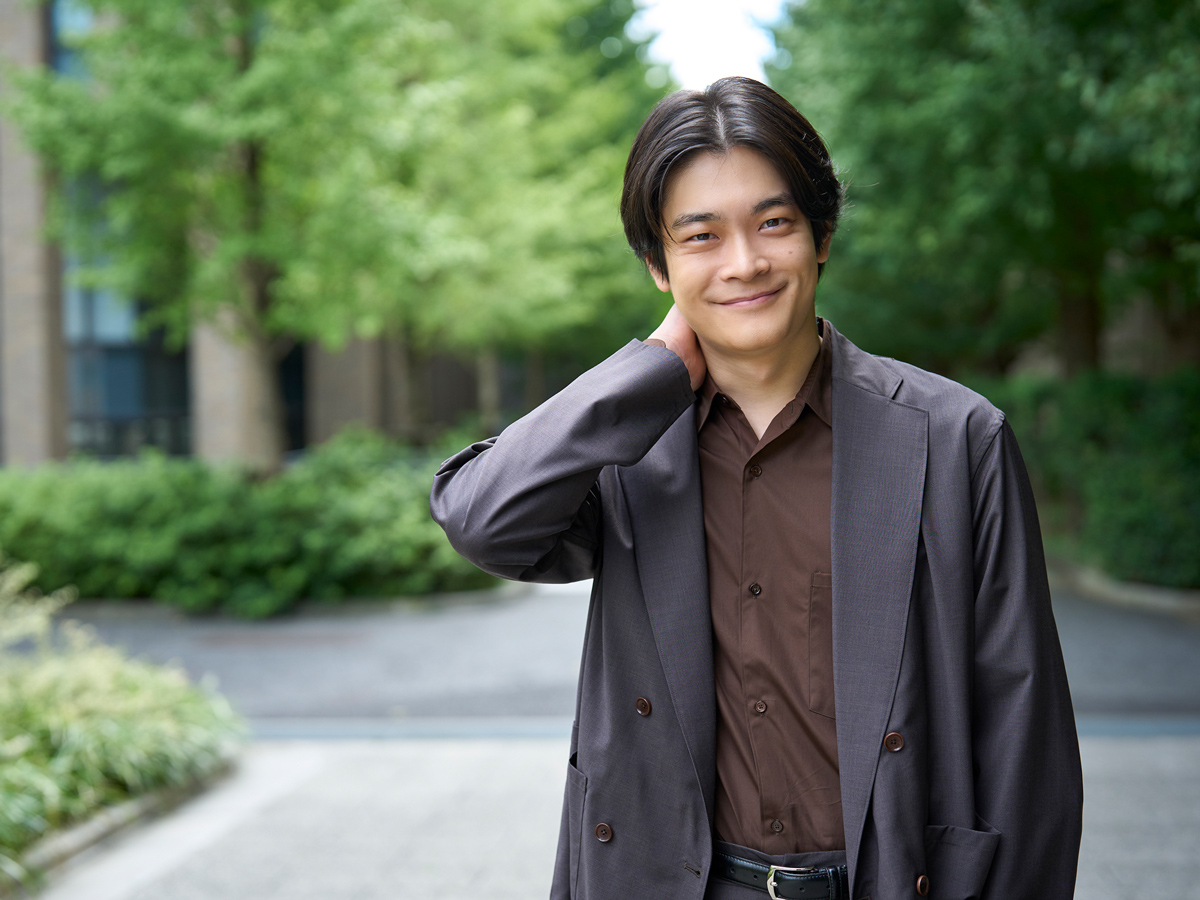リアルでいること
Q:メタフィクション的な演劇を撮影して映画にしたような印象もありました。ご自身は演劇をやっているような感覚はありましたか。
井之脇:その感覚はありましたね。リハーサルは10回以上やりましたし、そうやって緻密に作り上げていく感じがとても演劇的でした。また劇中劇で、行人と貴織が腕を駆使した芝居を行いますが、あの動きは2人を演じた大友くんと木竜さんが自分たちで考えて作ったものです。ポーランドの劇団の動きを参考に、七里さんが「人間の意志って肘や腕に宿るよね」と伝え、「あとは自分たちで考えてみてください」と2人に委ねた。その考える過程も役作りの一環だと。「2人の動きに関しては、井之脇くんは完成するまで見ないでください」と七里さんに言われたので、実際の撮影のときまで全く見ていませんでした。そういった“実際に作っていく感覚”みたいなものが、現場に漂っていた気がします。
Q:瞬介は図書館からなぜか出られないという状況に戸惑いつつも受け入れている感じもあります。瞬介という役をどのように捉えていましたか。
井之脇:受け入れているというよりは、受け入れざるを得ないと言う方が正しいのかなと。身体の迷子だけじゃなく、心の方もどうしたらいいか分かっていない。瞬介はたぶん大人迷子になっている。そんな受け身で迷子の瞬介が「やっぱり何かおかしい」と、この不思議な世界で自分から動き出すんです。

『ピアニストを待ちながら』©合同会社インディペンデントフィルム/早稲田大学国際文学館
Q:現場での監督の演出はどうでしたか。
井之脇:七里さんの求める芝居は、リアルに近く、とにかく“傾かない(歌舞かない)”ことだったと思います。それはOKの出され方を見て感じましたし、「基本的にゆっくりでいいよ」という言葉も示していました。これは余談ですが、「すべての道は役者に通ず」(著/春日太一 小学館)という本の中で、中井貴一さんが「僕はリアリズムを追求していきたい。それはナチュラリズムとは違うんですよね。」と話されていて、とても興味深いなと。僕らは“芝居”をしなきゃいけないけれど、“リアル”にやっていく。そのことは七里さんの現場でも意識していました。ただ何となくナチュラルにやるのではなく、相手にどういう影響を与えたらいいか落とし込んだ上でリアルにやっていく。それが七里さんの求める芝居でした。役者は皆それぞれに特性があるので、最初から七里さんに合う人もいれば、だんだん合っていく人もいる。七里さんは誰に対しても一貫していて、 “傾かず(歌舞かず)”等身大でいてくれと。言葉こそなかったものの、そう伝えていた気がします。