
向かって左よりクリストバル・レオン監督、ホアキン・コシーニャ監督、八代健志監督 © Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
『ハイパーボリア人』クリストバル・レオン監督&ホアキン・コシーニャ監督 × 八代健志監督 『オオカミの家』に続くアナログ手法の映画制作【Director’s Interview Vol.470】
チリの歴史や政治を題材に選ぶ理由
Q:『ハイパーボリア人』は、実在したチリの外交官でありナチス信奉者であったミゲル・セラーノ氏がモチーフになっています。前作『オオカミの家』にも共通するように、チリの歴史や政治を題材に作品を作ることはレオン監督とコシーニャ監督にとってどのような意義があるのでしょうか。
コシーニャ:まず一つは、日本との状況の違いです。チリでは映画だけではなくあらゆる芸術において政治や社会の問題を切り離して考えることが難しい。何か芸術をやるときは、政治的・社会的なことを取り入れ反映させていくことが、チリの芸術界においては常識であり普通なのです。私は日本の状況をよく知りませんが、もしかしたらそこが日本との大きな違いかもしれません。
二つめに、そういった政治的社会的背景をどのように芸術に取り入れるかはそれぞれのアーティストの考え方次第なので、それが常に芸術家として抱える問いでもあります。私たちの最近の作品『オオカミの家』『骨』(21)『ハイパーボリア人』は「昔のチリが抱えていた歴史的社会的背景を現代の社会の中でどう解釈し理解するのか」を反映させて作りました。それが少し奇妙に見えるのかなと思いますが、それが私たちの表現なのです。

『ハイパーボリア人』© Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
アナログ手法にしか出せない魅力
Q:CGの技術が上がっている昨今、あえてストップモーションや操演などのアナログな手法で表現することにどのような魅力があると思いますか。
レオン:まず、この社会はコンピューターを通した仕事が蔓延しています。もうこれ以上いいんじゃないの?というほど、コンピューターから離れられない生活になっている。それに対して手作業で作るものやストップモーションアニメは、頭を休める役割…、心身に安らぎを与えると言ったら言い過ぎかもしれませんが、そういった役割を持つものではないかと思います。
私たちは元々グラフィックアートの出身ではありません。文化的なものや絵など、造形物を作る美術分野の出身なんです。なので、映画は自分たちの分野をどう芸術に転化できるのかというチャレンジでもあります。その中で手作業とCGを比べてみると、やはりオリジナル性の高さでは手作業に勝るものありません。CGで作ると誰もが似たものを作り出せてしまうという一面がありますが、手作業で作ったものは全く同じものができることはなかなかありません。また特に私たちの作品は、ものを作るプロセスも映画の中に盛り込むことを大切にしていますが、CGではそれは難しいですよね。それに奇妙なものを作りたいときは、やはり手作業に限ると思います。
これは私だけではないと思いますが、手でものを作ることは、自分の中の無意識のレベルにある子供の心を呼び起こしてくれます。作っている間はとても自由になれますし、遊んでいるような気分になります。そうすると大人が忘れてしまった、幼児が持つ創造性のようなものが次々に出てくる。そういったことがCGでは全く起きないとは言いませんが、ただ私の場合はPCの画面の前にいるときよりも手でものを作っている時のほうが、はるかに無意識レベルの自分の子供が湧き上がってくる感覚があるのです。
八代:自分の中にある同じような感覚を違う言葉で起こしてもらったような感じです。僕も作品を作るときはとても近いことを考えています。
『ハイパーボリア人』を今すぐ予約する↓

向かって左よりクリストバル・レオン監督、ホアキン・コシーニャ監督
監督/脚本/美術/編集:クリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャ
2007年から活動をはじめた二人組のビジュアル・アーティスト。ともにチリ・カトリック大学を卒業。レオンはベルリン芸術大学とアムステルダムのDe Ateliersでも学んだ。ラテンアメリカの伝統文化に深く根ざした宗教的象徴や魔術的儀式を、実験映画として新しい解釈で表現している。映画制作のために、写真、ドローイング、彫刻、ダンス、パフォーマンスなど、さまざまな技法を組み合わせている。彼らのストップモーション映画は、洗練されていない映画的言語が特徴である。張り子の人形や無邪気な絵は、映画が扱う宗教、セックス、死といった重いテーマと強いコントラストを成している。彼らは各所で受賞歴があり、また、彼らの映画はロッテルダムやロカルノなど世界中の国際映画祭で頻繁に取り上げられている。展覧会も、ラテンアメリカの美術館やビエンナーレのほかに、ロンドンのホワイトチャペル・ギャラリー、ニューヨークのグッゲンハイム美術館、ベルリンのクンストヴェルケ現代美術センター、ヴェネチア・ビエンナーレ(2013)、スイスのアート・バーゼル(2012)などで開催されている。初の長編映画『オオカミの家』は、美術館、文化センター、アートギャラリーなど、さまざまな公共の場所でのノマドワーク・イン・プロセスのインスタレーション作品として制作された。2018年の第68回ベルリン国際映画祭でプレミア上映されカリガリ映画賞を受賞、アヌシー国際アニメーション映画祭で審査員賞を受賞するなど、各国で多くの賞を受賞。2021年にはwebサイト「IGN」の歴代アニメーション映画ベスト10に選出。同年Varietyの「観るべき10人のアニメーター」にも選出された。 『オオカミの家』に惚れ込んだ映画監督のアリ・アスターが製作総指揮を務めた短編『骨』は、第78回ヴェネチア国際映画祭でオリゾンティ部門最優秀短編映画賞を受賞。その後、トム・ヨークの新バンドThe Smileの2022年リリースのシングル「Thin Thing」のミュージックビデオを監督したことも話題に。さらに、アリ・アスターの監督作『ボーはおそれている』(23)では、アニメーション・パートの制作とビジュアル開発を担当。現在は、長編劇映画『LA PLAGA/THE PLAGUE』と、童話「ヘンゼルとグレーテル」から着想を得た長編アニメーション映画『HANSEL & GRETEL』のプリプロダクション中である。
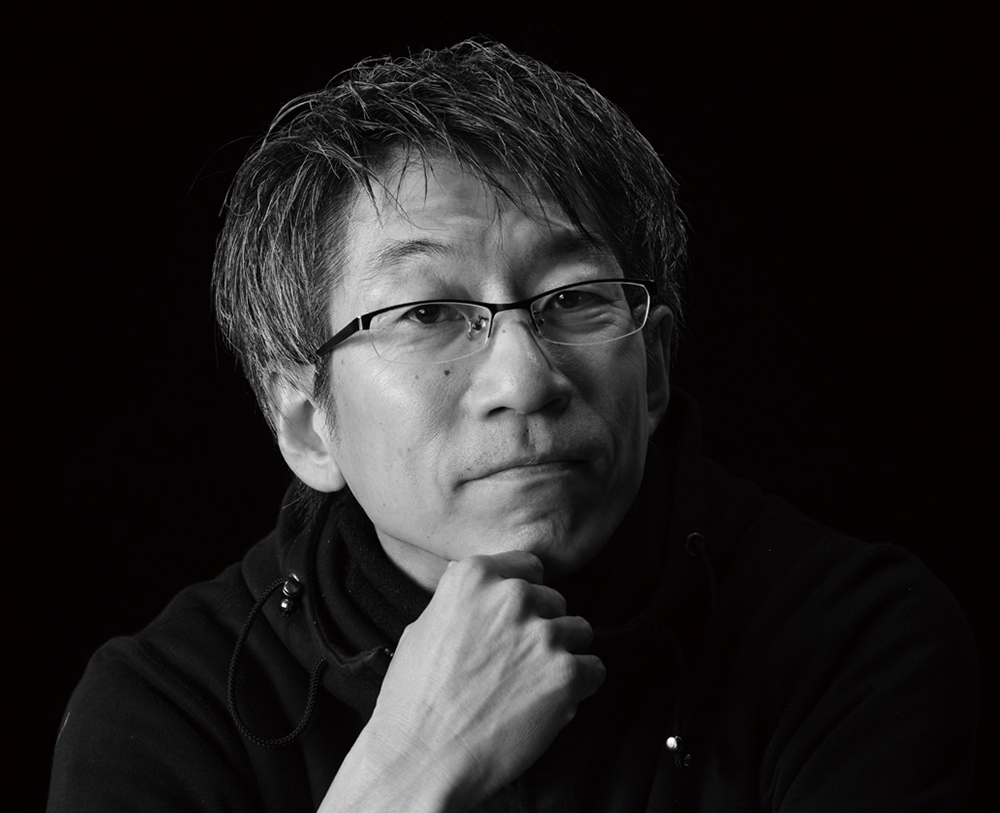
ディレクター/人形アニメーター:八代健志
東京芸術大学デザイン科卒業。太陽企画にて実写を中心にCMディレクターとして活動する傍ら、様々な手法のストップモーションアニメーションも扱ってきた。2015年TECARATを立ち上げ、人形アニメーションに軸足を移す。脚本・監督のほか、美術、アニメート、人形造形なども手がける。材料の素材感を重視した美術で、ストップモーションアニメーションならではの映像を目指している。
取材・文:阿部靖子
1988年生。フリーランスのストップモーションアニメーター。CMやテレビ番組のコマ撮り作品やNetflix『リラックマとカオルさん(19)』『リラックマと遊園地(22)』『PUIPUIモルカー DRIVING SCHOOL(22)』『ポケモンコンシェルジュ(23)』にアニメーターとして携わる。八代監督の『ノーマン・ザ・スノーマン』『眠れない夜の月』にも参加。コマ撮りアニメの魅力を伝えるブログ「コマコマ隊のコマドリル」運営メンバーとしても活動中。
『ハイパーボリア人』
2月8日(土)公開
配給:ザジフィルムズ
© Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films

