日本人史上最年少で第70回カンヌ国際映画祭シネフォンダシオンにノミネートされた、22歳の新鋭・井樫彩監督。自身初長編作品となる最新作『真っ赤な星』では、14歳の少女と27歳女性の心の機微を見事に捉えている。まるでベテラン監督が手がけたかのような、静謐で落ち着いた佇まいが画面を支配している本作だが、そんな映画の内容とは対照的に、井樫監督は終始満面の笑みでインタビューに応えてくれた。
Index
表現する手段がたまたま映画だった
Q:映画を拝見して、初長編作でよくあそこまで作り上げたなと感心しました。
井樫:ありがとうございます。
Q:監督は脚本も手がけてるんですよね。
井樫:そうですね、はい。
Q:どういった理由でこのお話を作ろうと思ったんですか。
井樫:以前、好きな女の子の友達がいて、岩井俊二監督の『リップヴァンウィンクルの花嫁』の話をその子としてたんです。あの映画って、お互いが唯一の存在で、相手のためなら死ねるよとか、そういう関係性の話なんですよね。それって、現実でもあり得るのかなって話をその子としたんですが、その話をした時点で、私とその彼女はそういう関係ではないっていうことが分かったんです。とても好きだと思ってたけれど、本当の深いところではつながってなかったんだなって、その時に感じて。
この、本当にすごく好きなんだけど、実は根本ではつながってないという関係性が、何か話にできそうだなって思ったんです。で、そのとき思い出したのが、『真っ赤な星』でも描いた、子供のころ自分が入院していた時に、看護師に泣かれたエピソードなんです。ふとそれを思い出して、あぁ、このふたつって何か掛け合わせられるんじゃないかなって。大人になった自分の話と、小さいころの自分の話を掛け合わせて、映画を作ってみようかなと思ったのがきっかけですね。

Q:映画を撮りたくてこの話を考えたのか、それとも、今言われたように話をふと思いついて、それを表現する手段がたまたま映画だったのか、どっちだったのでしょうか?
井樫:たまたまですね。たまたま映画でした。小さいころは漫画家になりたくて、ずっと絵を描いてたんですけど、とにかく最後まで出来ないんですよ。全然最後まで描けなくて。その時点で漫画は向いてないんだなと思いました。小説とかも書いたりしたんですが、それも続かなくて。唯一映画が、最後までできる表現手段だったんです。漫画や小説だと、自分でお話を書いて、絵を描いて。それで終わりじゃないですか。でも、映画となると、スタッフやキャストと一緒に作ることになるので、必然的に最後までやらざるを得ない状況に追いやられるんですよね。多分それが最後まで出来た理由だなって思います。
Q:面白いですね。逆はありそうですけどね。一人だと自分の中で全部完結できるから、気軽に始められる。でも映画って、今言われたように多くの人が関わるし、且つ自分がやりたいことを人に託す部分もいっぱい出てきますよね。
井樫:そうですね。
Q:それでも、映画のほうが最後まで出来たのは、やっぱり映画に向いてたってことなんですかね。
井樫:向いてるかどうか分かんないですけど、今のところ(笑)。
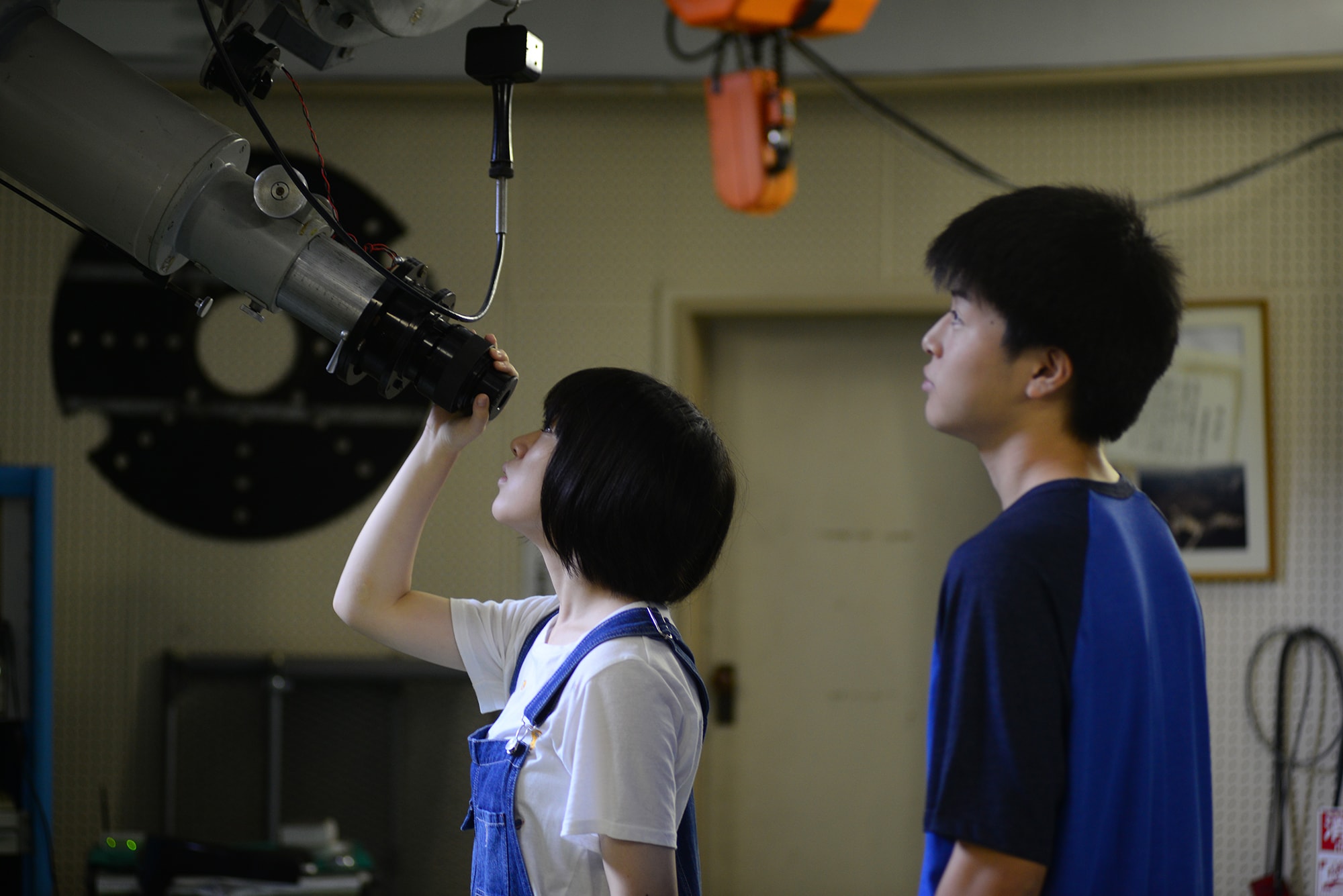
Q:強制的にやらざるを得ないっていうのは、面白い答えですよね。ある意味プレッシャーが、完成に追い立てるということなんですかね。
井樫:そうですね。その映画に対して作り上げたいって思いはもちろんあるんですけど、作っていくにつれて、一緒にやっているスタッフやキャストに対する思い入れみたいなのものも入ってくるんです。当初の作品自体への思いに、それがさらに上乗せされていく。プレッシャーと言うよりは、その人たちのためにも「やったるか!」みたいな感じかもしれません(笑)。
Q:いい監督ですね。
井樫:いや、暴言ばっかり吐いてるんで、いい監督じゃないです(笑)。


