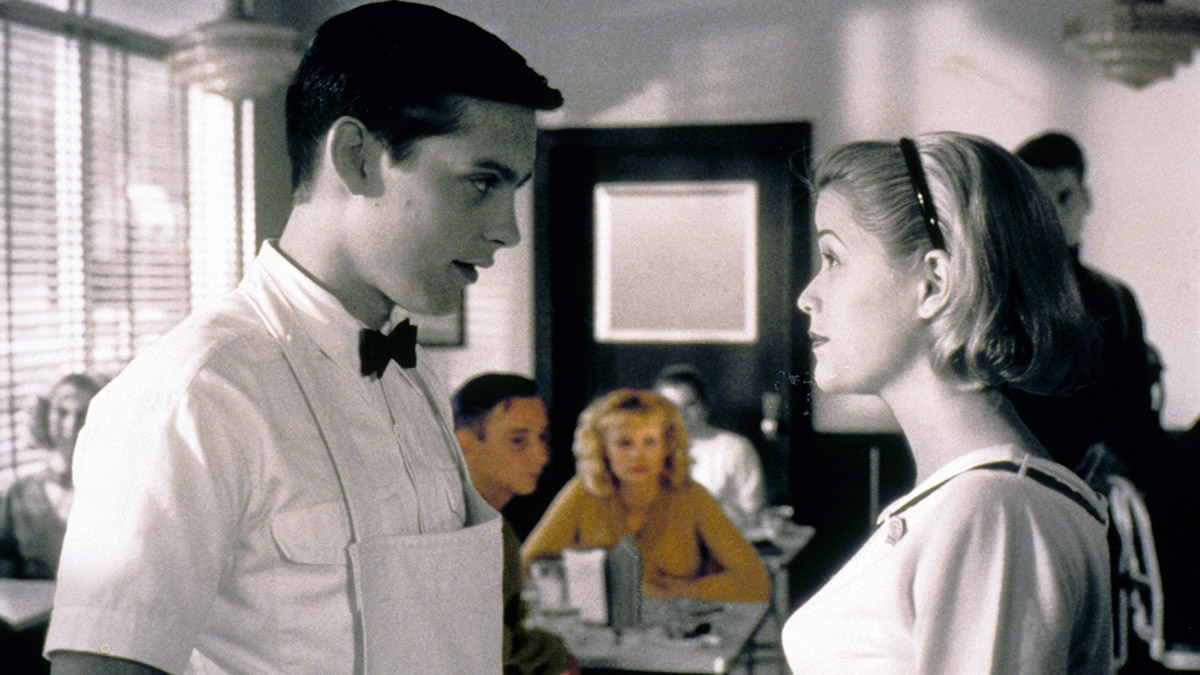2022.09.21
映画と色の関係
意図的に画面の色彩をコントロールした映画は、けっして少なくない。そもそも映画が誕生して間もない頃から、この考え方は存在していた。
まず染色という方法がある。これはシーン別にフィルムを染料に浸し、染めてしまう方法で、例えばナイトシ-ンならブルー、デイシーンは黄色、桜満開の春ならばピンクというように、その内容に合わせた色にするわけだ。でもこの方法の欠点は、ブルーならブルーのモノトーンになってしまうことだった。
日本人が撮影した最も古い映画とされる『紅葉狩』(1899)の赤染色版
それを自然なフルカラーに近付けるために考案されたのが、手彩色(*1)というテクニックだった。専門の職人が、1フレームずつ透明な絵具で塗って行くという方法で、やり方次第でかなりリアルな表現も可能だが、多額の予算と、特別に訓練された人材(主に女性が担当)が必要になる。例えば、『月世界旅行』(1902)で知られるフランスのジョルズ・メリエスは、専用の彩色工場も持っていた。アメリカでは、メリエスのライバルだったエジソン社のエドウィン・S・ポーターが、『大列車強盗』(1903)の手彩色版を作っている。
手彩色が用いられた『月世界旅行』(1902)
手彩色版『大列車強盗』(1903)
この面倒な作業を工業化したのが、ステンシル法というもので、色別に型となる穴の空いたフィルムを用い、カラーインクで印刷していくという方法である。これは、フランスで1903年に考案されたパテカラー(Pathécolor)、もしくはパテクローム(Pathéchrome)という技術が最初だった。だが、色別に小さな穴を切り抜いていく作業は困難を極める。そこで、フィルムをスリガラスのテーブルに拡大投映し、オペレーターが輪郭をなぞる。すると、パンタグラフという製図機に刃を取り付けた装置が人の手の動きを縮小し、フィルムをカッティングしていく機構が開発された。同様のアイデアは、フランスで活動していたスペイン人のセグンド・デ・チョーモンによっても、1911年にシネマコロリーズ(Cinemacoloris)として考案され、ゴーモン社に採用されている。
ステンシル法によるパテカラーで彩色された『Le Tour du monde d'un policier』(1906)
(*1)東宝では、鉄道省から委託された文化映画『鐵道信號』(39)において、演出の大石郁雄が信号機の色をカラーにするよう、線画(アニメーション)担当の鷺巣富雄(うしおそうじ)に要求した。鷺巣が困り果てている所に、上司の円谷英二が手彩色することを提案して実現させている。ただし彩色が実行されたのは、鉄道省に納品された初号プリントだけだった。
【参考文献】
うしおそうじ 著:「夢は大空を駆けめぐる‐恩師・円谷英二伝」角川書店(2001)
(*2)2005年に、京都の骨董商で映像文化史研究家の松本夏樹氏が発見した、50フレームのループフィルムには、ステンシル法で着色されたアニメーションが写っており、『活動写真』という仮題が与えられた。バイエルン州立図書館研究員のフレデリック・S・リッテン博士による調査で、1907年前後に制作されたものと判明する。これによって、日本におけるアニメーションの誕生時期が、従来の定説から10年も遡り、欧米とほぼ同時にスタートしていたことになる。
【参考文献】
渡辺泰/松本夏樹/フレデリック・S・リッテン/中川譲 著:「にっぽんアニメ創生記」集英社(2020)