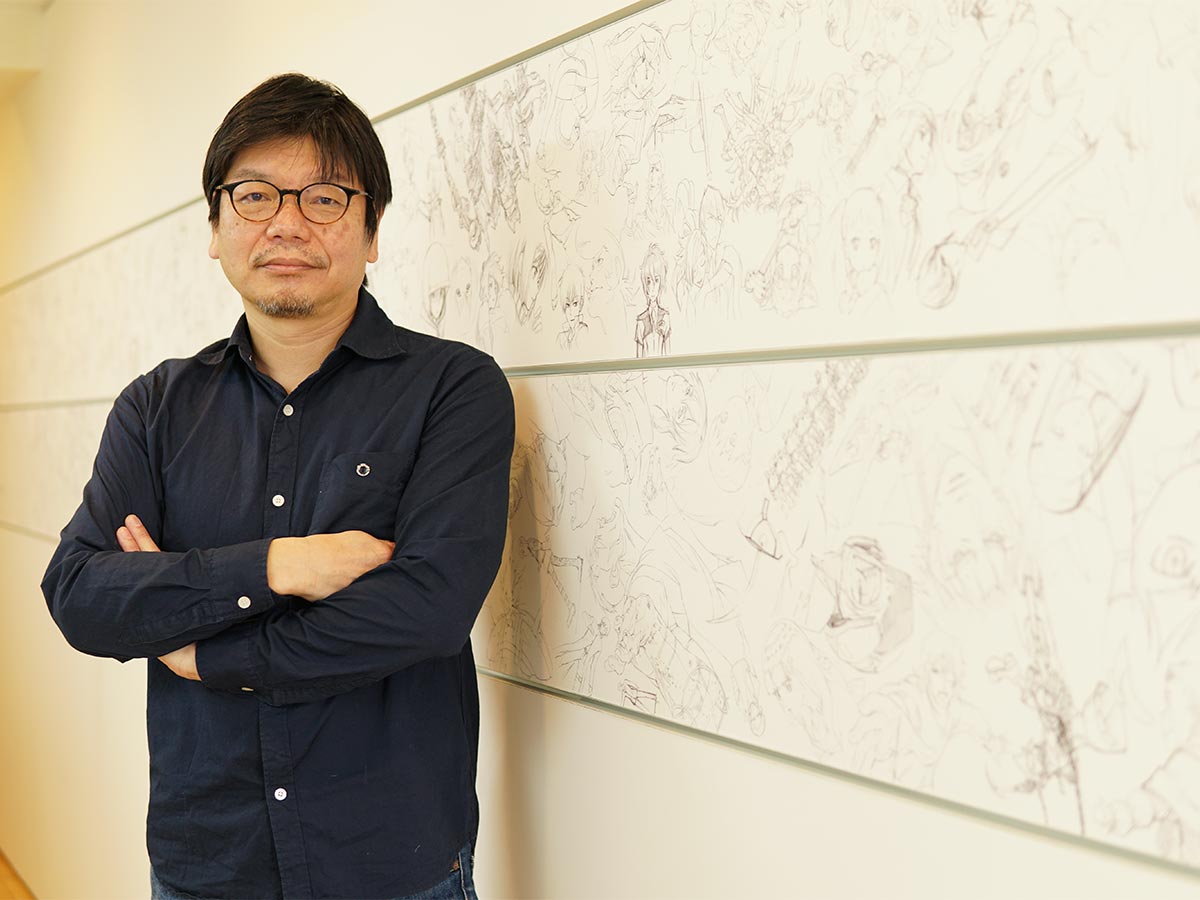原作のファンタジー性とアニメならではの表現は好相性
Q:いまお話しいただいた「ボンズがアニメ化する」必然性・絶対性は、完成品を観ると痛感するのですが、作品を作る前の時点では、いかがだったのでしょうか。
南:実写版はすごくリアリティがあるものだったと思いますが、「ジョゼと虎と魚たち」という原作自体には、多分にファンタジックな要素が入っていると感じていました。
アニメーションって、絵で表現されている以上、絶対ファンタジーになっちゃうんですよ。絵で描かれているからこそ、もしかしたら実写以上に人間の関係性や心情を浮き上がらせることもできる。本作のジョゼと恒夫の出会いって、ある種の奇跡じゃないですか。全く違う環境にいた2人が出会って、新しい世界が始まる。その姿をアニメーションで描くのは面白いし、アニメーションならではの魅力を生かせる題材のようにも思いました。
このところ、現代劇が増えている背景もありますよね。新海誠監督たちの影響もあるでしょうし、アニメーションが“その時代”の少年少女たちを描く、という流れがある。そういう環境があるからこそ、『ジョゼと虎と魚たち』のような企画が上がってきたのかな、ととらえています。どっちかっていうと、うちは未来や近未来の話が多いんですけどね(笑)。

Q:タムラ監督も、お話を伺った際に「令和の物語にすることを意識した」とおっしゃっていました。
南:原作が書かれたのは昭和(1984年に発表)ですから、その時代性をそのまま今に持ってくるよりは、原作自体を今に持ってきて、2人の関係性を描くほうが正しいとは思いますね。この作品は男女の恋愛ものというよりは成長物語ですし、2人が共有していく“時間”を描き、観てもらうことにすごく意味があると感じました。
作品を観ていただくと、引いた画が多いことに気づくかと思います。2人をすごく温かく見ている“誰か”、それは観客自身につながると思うのですが、そういった温かみを感じさせる映像になっているんですよね。
映画自体のメインターゲットは、ジョゼや恒夫と同世代の20代の男女かとは思うのですが、それより下の世代にも、お兄さんお姉さんの恋愛を見守る感覚で観てもらえたら嬉しいですし、自分なんかは孫を見守るような感覚になりましたね。じつはかなり幅の広い映画になっています。