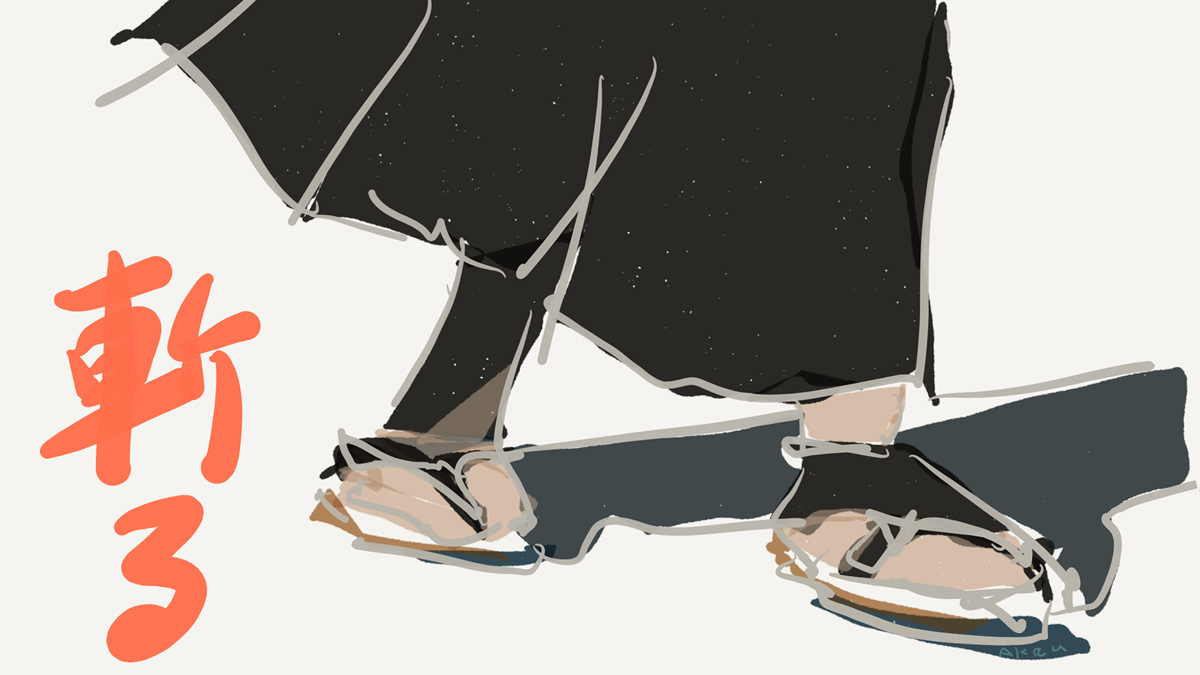『斬る』を挟んで作られた2本の戦争映画
ところが『斬る』は、その面白さに比して語られることが少ない作品でもある。喜八監督が後々に『斬る』を振り返って語っている資料もあまりない。“戦争”というテーマにこだわり続けた作家性を語る上で欠かすことのできない2本の重要作、『日本のいちばん長い日』(67)と『肉弾』(68)の狭間で撮られたことも影響しているのだろう。
太平洋戦争の敗戦を国民に告げた「玉音放送」の顛末を描いた『日本のいちばん~』は、当初『人間の條件』(59~61)の小林正樹が監督する予定だったが紆余曲折があり、東宝の社員監督だった喜八に任された経緯がある。東宝創立35周年記念大作として1億9,000万円の巨費が投じられ、観客動員は100万人を超え、当時の東宝映画の興行記録を塗り替えた。関係者ですら予想をはるかに超える業績に驚いたという。
1991年に出版された書籍「kihachi フォービートのアルチザン」に、67年8月22日の東京新聞に掲載された談話が引用されている。『日本のいちばん~』大ヒットの褒美として「東宝が次回作に大作を準備している」という話を受けて、喜八監督は「好意はありがたいんだけど、その間にボクの体質に合った、はじめから終わりまでアクセルを踏みっぱなしみたいな小品を撮りたいなア」とコメントしている。

『斬る』イラスト:村山章
このとき喜八監督が「ボクの体質に合った小品」として思い浮かべていたのは、数年前にすでに脚本を書き上げていた『肉弾』だったに違いない。喜八は、政府や軍の上層部ばかり登場する『日本のいちばん~』を一種の「雲の上の話」と捉えて、自らの戦争体験を重ね合わせた名もなき一兵卒の物語『肉弾』を通じて“庶民から見た終戦”を描き出そうと考えていたのだ。
しかし悲願の企画『肉弾』は東宝から拒否され、喜八は日本アート・シアター・ギルド(ATG)の「一千万円映画」として製作費の半分を個人負担し、ほとんど自主映画に近い体制で実現に漕ぎ着けた。結果として『日本のいちばん~』と『肉弾』は、対で語られるべき伝説的な2本になった。