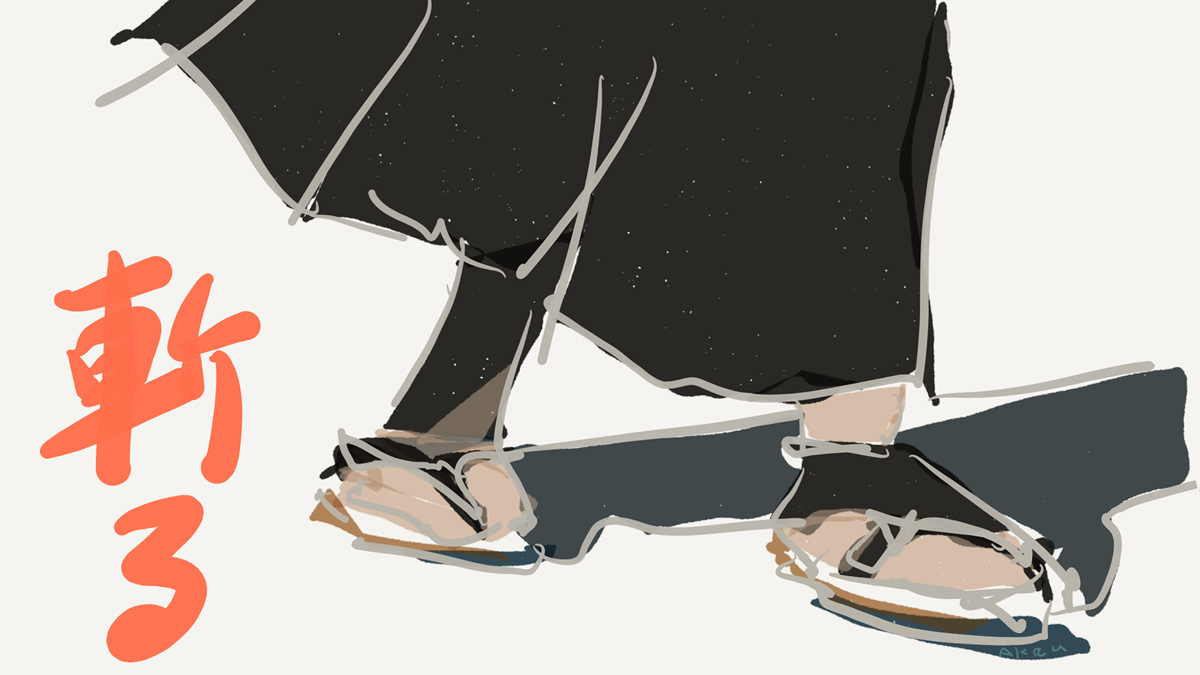反骨精神が打ち出した“アンチ侍”スピリット
また、『斬る』が階級社会を皮肉っているのは冒頭だけではない。映画全体を通じて幾度も「侍なんてくだらない」という問いかけが繰り返される。
いくら高潔であろうとしても、権力はいつか腐敗するし、名誉や忠義を重んじれば窮屈なしがらみに縛られる。大義名分を掲げたところで、人を斬ることはただの殺人でしかない。セリフの端々だけでなく、戦いの場面で挿入される残酷なインサートカットや、武士の誇りであるはずの剣技に決定的な活躍の場が与えられず、それどころかほとんど禍いしか呼ばない展開など、喜八監督の強いこだわりは作品の随所に現れている。

『斬る』イラスト:村山章
源太は、侍が見向きもしない身分である自分たちのことを「虫けら」と嘯いて笑い、荒尾十郎太は「得体が知れないのはわれわれも同じ」と自嘲する。しかしこの映画では、思想や名誉や利益のためでなく、純粋に誰かのために身を捨てて動くのは彼ら「得体の知れない虫けらたち」なのである。
最初は理想に燃えていた若侍たちが、しだいに追い詰められて仲違いしていく流れは原案となった「砦山の十七日」の通りだが、喜八監督の「侍なんてのは、そんなに強くって偉くってってなもんじゃないだろう。やっぱり人間臭い、おかしいとかみっともないとか、そういうものじゃなきゃ俺とは繋がらない」(「kihachi フォービートのアルチザン」掲載のインタビューより)という発言とも符合する。
また彼らが大義のために決起する姿は、『日本のいちばん~』の暴発する青年将校たちと重ねることもできる。暴力の純粋さと危うさを表裏一体として語る『斬る』には、間接的ではあっても反戦の思いが確実に宿っており、喜八監督のキャリアにおいて、間違いなく『日本のいちばん~』以降、『肉弾』以前の必然として語られるべき作品だと考えている。