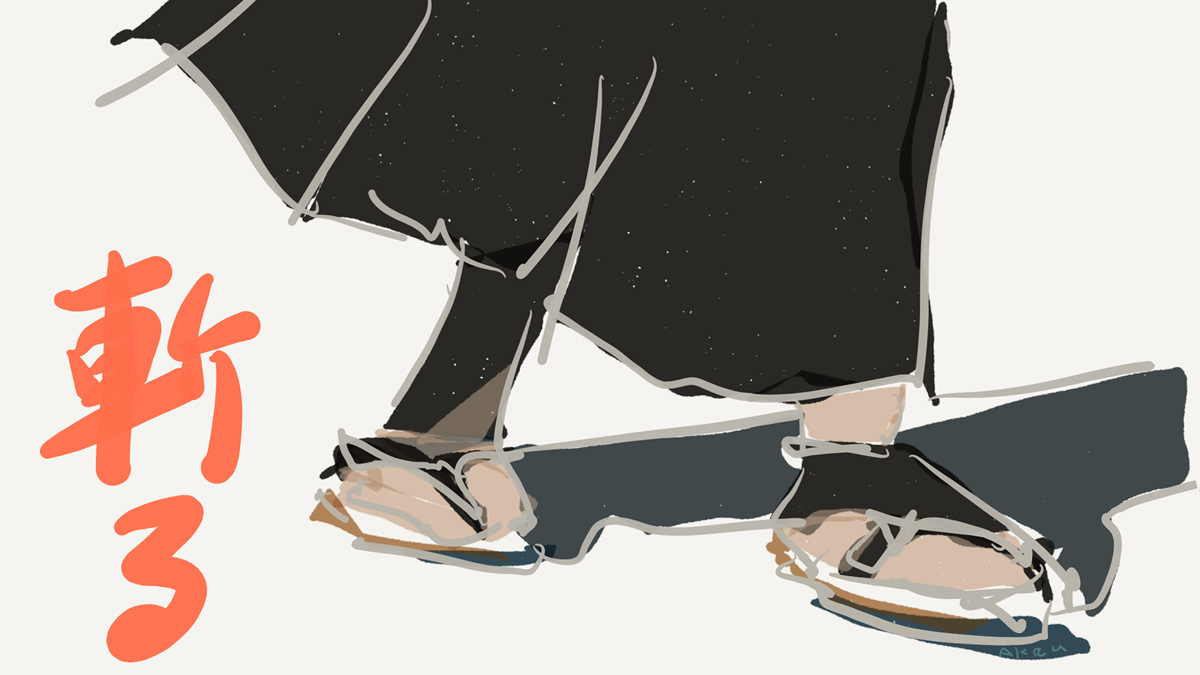東宝VS変化球を投げる問題児
一方で、喜八が『日本のいちばん~』の後に、本来のホームである東宝で着手したのが『斬る』だった。前述の記事にあった「褒美としての次回作」だったかどうかは不明だが、68年2月26日の読売新聞夕刊では「初めての“ぼくらしい”時代劇になるだろう」と抱負を語っている。
額面通りに受け取るなら、それまでに撮った時代劇は「ぼくらしくない」作品だったことになる。実際にはどの作品にも色濃く喜八監督らしさが宿っているのだが、いずれも喜八本人の発案ではなく、会社の主導で撮ることになった企画ではあった。
余談として、『斬る』に至るまでに、喜八監督と東宝の間で作風をめぐる攻防が深刻化していた裏事情にも触れておきたい。
1943年に東宝に入社し、長年助監督を務めた岡本喜八は、58年に『結婚のすべて』で監督デビュー。おりしも日本の観客動員数がピークを迎えた年で、時代の追い風に乗って監督作を連発する。翌59年には自ら脚本を書いた戦争アクション活劇『独立愚連隊』を発表。西部劇を彷彿とさせるカラリとした作風で時代に新風を巻き起こす。さらに62年には愚連隊シリーズ第三弾『どぶ鼠作戦』が配給収入1億8,900万円の大ヒットとなり、東宝の看板監督のひとりとなった。
しかしありきたりを嫌ってトリッキーな表現を駆使し、ユーモアにまぶして戦中派としての反権力、反戦の想いを刻み込むアプローチは、無難なヒット作を求める東宝の上層部との間に齟齬が生まれていた。

『斬る』イラスト:村山章
特に“喜八タッチ”を突き詰めた傑作としてファンに愛されている『江分利満氏の優雅な生活』(63)と『ああ爆弾』(64)は大コケし、今ではカルト人気を誇る『殺人狂時代』(66)は公開中止に追い込まれた(後に一週間限定で公開)。しかもこの3本は東宝で手掛けた数ある監督作の中でも、観客動員でぶっちぎりのワースト3だったのだから、会社側にも言い分はあった。
かくして東宝は喜八に“変化球監督”の烙印を押した。喜八本人が提出するオリジナル企画は却下し、大御所の脚本家と組み合わせようと考えた。そうして生まれたのが黒澤明作品などで知られる橋本忍脚本による『侍』(65)や『大菩薩峠』(66)、『日本のいちばん~』だったのだから、会社としても喜八の手腕を高く評価していたことは伺える。ただし撮りたいものが撮れないフラストレーションは、喜八の中で着実に蓄積していった。