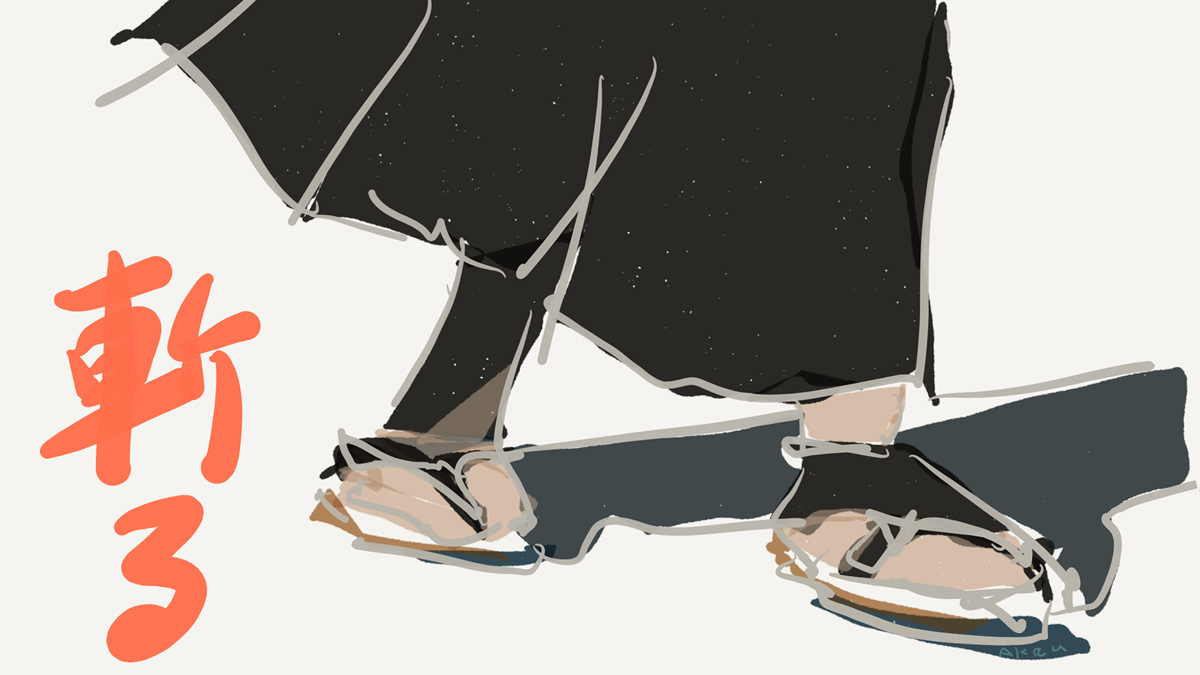庶民のパワーが押し寄せる怒涛のクライマックス
最後にもうひとつだけ、あまりにも喜八監督らしい場面について触れたい。
映画の終盤、陰謀の黒幕の屋敷で大乱戦となるクライマックスで、それまで姿を見せなかった百姓たちが大挙として押し寄せてくる。近づいてくる太鼓や笛の音を聞いて、若侍のリーダー哲太郎(中村敦夫)が「百姓がわれわれに手を貸そうというのか?」と驚くと、源太の舎弟になったヤクザの武助(樋浦勉)が叫ぶ。「ケッ! 何が侍なんぞに! 祭りだよ、百姓たちはこの2年越し太鼓も樽も叩いたことがねえんだ、みんな大喜びだぜ!」。
実はこの場面は、もともとの脚本には存在していなかった。少なくとも映画公開の約2ヶ月前にキネマ旬報(昭和43年4月下旬号)に掲載された脚本では、江戸から大目付が到着したところで事態が収束しており、後の『ジャズ大名』(86)にも繋がるお祭り騒ぎのカタルシスは描かれていない。おそらく撮影が始まる土壇場の修正稿か、撮影中に新たに追加されたものだと思われる。

『斬る』イラスト:村山章
また前述の脚本では、大目付の到着も、ノンポリに見えていた次席家老・森内兵庫(東野英治郎)が裏で手を回していたことが明かされる。しかし完成した『斬る』ではそのくだりはカットされており、老家老の機点で混乱が収束するどころか百姓の乱入でさらに大騒ぎになり、カオスな高揚感から新たなる旅立ちを描く粋なエピローグへと繋がっていく。
あらゆる権力や権威に舌を出し、はぐれ者や庶民の側に立とうとする喜八監督のスタンスは助監督時代に書いた『独立愚連隊』から一貫しているが、『斬る』を撮ったときは44歳。デビューから10年を経ての22作目の監督作であり、まさに脂の乗っている時期。映画職人としての腕前と自分らしさを両立させるには絶好のタイミングだっただろう。逆にいえば『斬る』は、それまでに培ってきた手練手管や得意技の全部出しであり、監督本人にとっては「こんなことはできて当たり前」な作品であったのかもしれない。
しかし、映画史に残る作品として語り継がれる喜八作品は数あれど、『斬る』こそが“東宝喜八映画”の集大成となる大傑作であることは議論の余地なしだと思うのだがいかがだろうか? まずはこのべらぼうに面白い映画をご覧いただいて、各々の目で判断していただきたい。
《参考資料》
「kihachi フォービートのアルチザン 岡本喜八全作品集」発行:東宝株式会社出版事業室
「岡本喜八全仕事データ時点」編著:寺島正芳
「キネマ旬報昭和四三年四月下旬号掲載 「斬る」脚本」発行:キネマ旬報社 脚本:岡本喜八、村尾昭 原作:山本周五郎「砦山の十七人」より
文: 村山章
1971年生まれ。雑誌、新聞、映画サイトなどに記事を執筆。配信系作品のレビューサイト「ShortCuts」代表。
イラスト:村山章