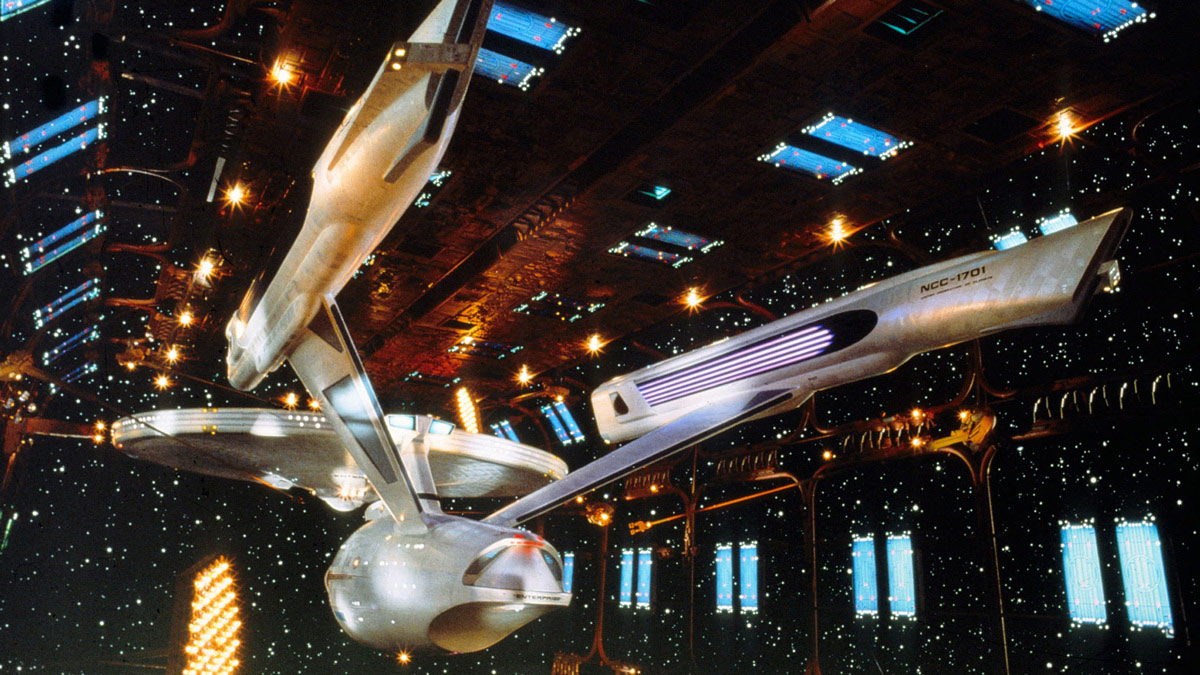ダグラス・トランブルへの打診
パラマウントは、劇場版『スター・トレック』の製作発表が行われるより前に、スペシャル・フォトグラフィック・エフェクト・ディレクター(*6)としてダグラス・トランブルを選んでいた。なぜなら、彼がCEOを務めるフュチャー・ジェネラル・コーポレーション(以下FGC)は、パラマウントの子会社だったからである。
FGCは1975年に設立された会社で、トランブルと長年コンビを組んでいるリチャード・ユーリシッチ(*7)が、次世代の映画システムを開発する企業としてスタートさせた。彼らはFGC設立以前から3D映画や、同じフィルムを2台のプロジェクターを用いて、わずかにタイミングをずらして映写することで、映画からフリッカーを追放するといった研究を繰り返していたのだ。
だが一向に成果が上がらない中で、1974年に効果的な実験結果が出たアイデアが2つだけ残った。まず、撮影・映写速度を従来の24fps(秒24フレーム)から60fpsに上げるというシステムで、フィルム特有のフリッカーやストロビングといった問題を解消できるというものだった。同時にフィルムサイズも70mm 5P(パーフォレーション)にすることで、画面の精細度も上げられる。彼らは、これを「ショースキャン」(SHOWSCAN)(*8)と名付け、パラマウントの幹部たちを集めて大劇場でデモを行った。この時、パラマウント社長のフランク・ヤブランズは、「この方式で映画を作らないとしたら、僕らは馬鹿だ」と語り、ショースキャン実用化のための研究施設として、FGC設立のためG+Wとパラマウント・ピクチャーズが全額出資した。
トランブルたちが2つ目のアイデアとして考案したのが、劇場全体を映像に合わせて油圧式アクチュエーターで揺らす、「シネライド」(Cineride)というシステムだった。これは現在、東京ディズニーランドで運営されている「スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」と基本構造は同じもので、4DXなどの元祖でもある。そして1974年に試作システムが作られ、1976年に遊園地業界向けの展示会IAAPA(国際アミューズメント&アトラクション協会)に出展されて、ベストニューアイデア賞を受賞している。
『未知との遭遇』予告
トランブルらは、ショースキャンとシネライドを劇場向けに実用化するために夢中で、普通の映画の視覚効果には一切興味を失っていた。そのため『未知との遭遇』(77)を例外(*9)として、『スター・ウォーズ』の依頼も断っており、同じ理由で『スター・トレック』の仕事も拒否した。
カッツェンバーグは、トランブルに監督を任せるという案も用意していたが、社内に反対意見が多くて却下されている。その理由は、ショースキャンを熱狂的に支持していたヤブランズが1974年11月にパラマウント社長を辞め、新たに社長兼COOとなったアイズナーはトランブルと折り合いが悪かったのである。
*6 意味としてはVFXスーパーバイザーと同じだが、この時代はまだアメリカで英国式のビジュアル・エフェクトという呼称が普及していなかった。
*7 リチャード・ユーリシッチは、『ベン・ハー』(59)、『ポセイドン・アドベンチャー』(72)などのマットペインターとして有名な、マシュー・ユーリシッチの弟である。高校卒業後にアニメーション会社に入社して、オプチカル合成やモーションコントロールの原型を学ぶ。その後『2001年宇宙の旅』を経て、CMのカメラマン助手を経験し、トランブル・フィルム・エフェクツに入社した。ちなみにマシューも『スター・トレック』のマットペイントで参加している。
*8 筆者が初めてショースキャンを観たのは、科学万博‐つくば’85「東芝館」の『Let's Go! パル』だったが、ミニチュアの塗装の刷毛跡まで見えてしまって興醒めした。その後いくつかのショースキャン作品を観たが、ドキュメンタリーなどには非常に有効で、特に水の流れは本物に見える。だがこの過剰なリアリティが災いし、ドラマではセットはセットに、カツラはカツラに、メイクはメイクにしか見えなくなり、造り物の不自然さを際立たせる結果となった。そしてトランブルは、1989年にこの分野から撤退してしまう。
その後トランブルは、2010年より再びハイフレームレート(HFR)技術に取り組み始め「ショースキャン・デジタル」という名前で研究を開始し、現在は「MAGI」(発音はマジャイ)という名称になっている。基本的に4K、120fpsのデジタル3D映像をベースに、48fpsや60fps、120fpsの映像を作り出すというものだ。この技術を用いた最初の作品は、トランブルの監督による短編『UFOTOG』(14)である。
アン・リー監督は、『ビリー・リンの永遠の一日』(16)や『ジェミニマン』(19)を120fpsで3D撮影するにあたって、トランブルにアドバイスをもらっている。
*9 トランブルは『未知との遭遇』の仕事をあっさり引き受けた。スピルバーグ監督は「彼は僕の脚本やアイデアをとても気に入ってくれた」と語っているが、『未知との遭遇』の配給会社がコロムビアであるため、パラマウントとの間に弁護士が入っての調整が必要だった。トランブルがこの企画に積極的だった理由については明確に語っていないが、1969年にカリフォルニア州ジャイアントロックで開催されたフライングソーサー(空飛ぶ円盤/UFO)・コンベンションに参加した経験を持っている。また最近は、莫大な私財を投じてUFOハンティングを続けており、元々UFO事件に興味があったと思われる。